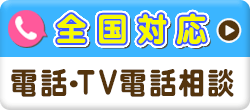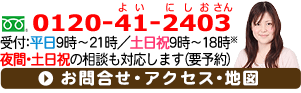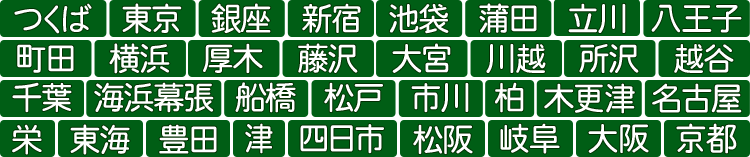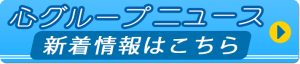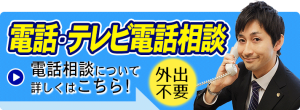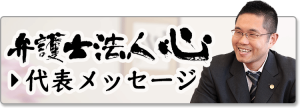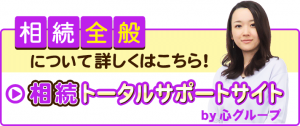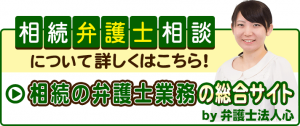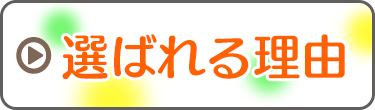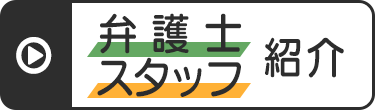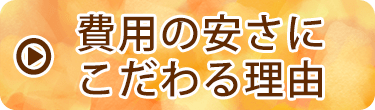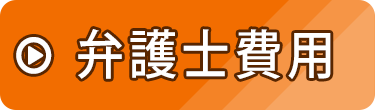相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
1 相続放棄は各相続人がそれぞれ行わなければならない 2 先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移る 3 被相続人が死亡した後、相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合 4 名古屋周辺の相続放棄の状況
1 相続放棄は各相続人がそれぞれ行わなければならない
⑴ 相続放棄は1人ひとり行う
相続放棄は、裁判所に対して被相続人の相続を放棄する旨を記載した書類を提出して行います。
この書類を「相続放棄申述書」といいます。
相続放棄は相続人の個々の意思表示であるため、ある相続人が、他の相続人の分まで相続放棄の手続きをするということはできません。
つまり、相続人が複数いる場合、ある相続人が相続放棄をしても、他の相続人は依然として相続人のままということになります。
⑵ 他の相続人への影響
相続人のうちの誰かが相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。
そうすると、他の相続人は、相続分が増えます。
被相続人に子が3人いる場合、原則としては子らの法定相続分は3分の1ずつですが、子のうち1人が相続放棄をすると、相続人としての子は2人だけだったことになるため、相続放棄をしなかった子らの法定相続分は2分の1ずつとなります。
相続財産が多い場合には、相続放棄をしなかった相続人は得をする形になります。
しかし、通常は相続する負債が多い場合に相続放棄がなされることが多いので、一部の相続人だけが相続放棄をすると、知らないうちに残りの相続人が負担する債務が増えてしまうということもあり得ます。
⑶ 複数相続人がいる場合の相続放棄の適切なタイミング
そのため、相続人同士で連絡を取り合うことができるのであれば、被相続人に多額の負債がある等相続放棄をした方がよい場合には、同じタイミングで相続放棄をした方がよいです。
また、被相続人を同じくする複数の相続人が一緒に相続放棄の手続きをすると、裁判所に提出する被相続人の戸籍謄本類等の共通した添付資料は1通で済むため、時間と手間を減らすことができます。
2 先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移る
⑴ 相続の順位
第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、たとえば被相続人の子全員が相続放棄をすると、子がいなかったことと同じになり、第2順位の直系尊属(通常は被相続人の両親)が相続人となります。
被相続人がお年を召した方であると、直系尊属もお亡くなりになっているケースが多くあります。
その場合には第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
年代が高い方は、ご兄弟姉妹が多い場合が多いため、相続人が急激に増えることがあります。
さらに、ご兄弟姉妹が疎遠であったりすると、お名前や連絡先を調べるだけでも大変な労力となります。
そのような場合、次順位の相続人の方に迷惑を掛けることを防ぐため、法律の専門家が委任を受けて連絡先を調べ、先順位の相続人が相続放棄をして旨及び兄弟姉妹の方が相続人となった旨を伝えることがあります。
ちなみに、相続放棄の申述の期限は、相続の開始があったことを知った日から3か月です。
そのため、被相続人の兄弟姉妹の方に連絡がなされるまでは、原則として申述の期限は開始されません。
⑵ 代襲相続が発生している場合の相続人の数
これは兄弟姉妹の方に限ったことではなく、被相続人の子が既に亡くなっていて、その子がいる場合にもあてはまることですが、被相続人の年齢が高い場合には、その兄弟姉妹も高齢で既に死亡していることも多く、代襲相続が発生して相続人が多数となるケースが多くあります。
こうなってしまうと、相続人の数が多いことに加え、親戚関係も希薄になってしまうことが多いため、調査や連絡が非常に大変になります。
3 被相続人が死亡した後、相続人が相続放棄をしないまま死亡した場合
代襲相続とは逆に、被相続人が死亡したときには生存していた相続人が、遺産分割協議も相続放棄もしないうちに亡くなってしまった場合は、その子などが被相続人の相続財産を相続することになります。
被相続人が多額の負債を抱えているような場合は、その子らに負債が降りかかってきます。
このようにして被相続人の相続財産を相続する人が何人もいると、相続放棄の検討をしなければならない人が増えます。
まず、相続関係を明確にしたうえで、誰がどの割合で被相続人の相続財産を相続しているのかを整理し、相続放棄を行うかどうかを決めることが大切です。
4 名古屋周辺の相続放棄の状況
名古屋周辺にお住まいの方で、相続放棄についてご相談をいただくことが増えています。
相続放棄は、簡単な手続きではありません。
正確には、相続放棄のための書類を書くだけであれば難しくはないかもしれませんが、相続関係が複雑な場合の添付書類の収集や、書類提出後の裁判所からの質問への対応、残置物の取扱い、債権者への対応など、専門知識を必要とする場面が多数あり、対応を間違えると相続放棄が認められなくなる可能性もあります。
相続人が複数いる場合は、必要な書類も多く、特に注意が必要です。
名古屋周辺にお住まいで、相続放棄をご検討されている方、特に相続人が複数いる場合や、次順位の相続人が複数いらっしゃる場合は、相続放棄の分野を得意とする弁護士に相談されることをおすすめいたします。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の固定資産税の支払い
- 相続放棄と光熱費
- 相続放棄で代襲相続は発生するか
- 相続放棄はいつまで行えるか
- 相続放棄と亡くなった方の家の片づけ
- 相続放棄をした場合、他の相続人への通知は必要か
- 相続放棄申述書の書き方
- 相続放棄における相続の順位
- 相続放棄と裁判所からの呼び出しの有無
- 相続放棄が認められないケース
- 相続放棄をしたかどうかについて確認する方法
- 相続放棄をすべき人
- 相続放棄の期限の始期
- 相続放棄の期限が迫っている場合について
- 相続人が複数いる場合の相続放棄の注意点
- 相続放棄と債権者対応
- 相続放棄とお葬式費用
- 相続放棄の期限の延長
- 相続放棄と生命保険
- 相続放棄の申述に必要となる書類
- 相続放棄の期限
- 相続放棄の理由
- 相続放棄を弁護士に依頼すべきパターン
- 相続放棄をしても遺族は年金を受け取ることができるか
- 相続放棄ができないケース
- 亡くなる前から相続放棄はできるのか
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
(愛知県弁護士会所属)
0120-41-2403